いとばや先生(糸林 誉史|文化人類学者)
専門|文化人類学・アクターネットワーク理論
日常に隠された「モノと人のご縁」を探求する専門家
糸林誉史|文化人類学者
早稲田大学大学院博士課程に在籍中、インドネシア大学とシンガポールのユソフ・イシャク研究所(ISEAS)に留学しつつフィールドワークを行い、文化・社会人類学の手法を身につけたいとばや先生は、今もフィールドワークを重視する研究者である。先生の研究は、学生時代の東南アジアの国際移民とコミュニティ形成の研究から始まり、その後、多様な主題へと展開していった点に特徴がある。

教員となってからの研究の変遷は、先生の知的探求の軌跡そのものである。まずシンガポールのコミュニティ自治と社会的ネットワークを分析し、BBCやNHKといった国際的な放送局のドキュメンタリー番組制作過程を民族誌的に研究した。この時期、先生は海外の日本人団体や日本人学校の研究も手がけ、『戦後アジアにおける日本人団体』の共著者として、引揚げから企業進出に至る日本人の移動とコミュニティ形成の歴史を明らかにした。
研究の焦点は次第に、伝統産業とコミュニティの関係へと移っていく。沖縄、韓国、マレーシアの民俗服飾を比較研究し、伝統がいかに創造され、継承されるのかを、アクター・ネットワーク理論の視点から解明した。現在の研究テーマは、市場的価値と社会的価値の関係性である。伝統染織の読谷山花織を事例に、職人、行政、消費者、市場が織りなすネットワークの中で、いかに持続可能な発展が実現されるのかを追究している。
先生の研究活動を支えてきたのは、継続的な競争的資金の獲得である。1999年の「シンガポールにおける多文化主義に関する研究」を皮切りに、2000年代前半には新聞広告とエスニック・アイデンティティ、国際共同制作テレビドキュメンタリーの研究で科研費を獲得した。2008年からはマレーシア・韓国・日本の近代化以前の日常着の生活史研究に取り組み、2011年からは「地域社会と民俗服飾」の基盤研究で5年間にわたり質的分析によるフォークロリズム研究を展開した。そして2020年から基盤研究「市場と価値の人類学」により、伝統染織の内発的発展に関する統合的研究を完遂している。現在は、沖縄の伝統産業の知識創造理論の研究と調査、その応用としての伝統産業の技能継承問題に取り組んでいる。
特筆すべきは、コロナ禍においてオンライン受講でキャリアコンサルタント国家資格を取得し、その知見を沖縄の伝統産業における技能継承や後継者育成の研究に活かしている点である。人類学者としての視座とキャリア支援の実践的知識を統合する姿勢は、学問と社会をつなぐ先生の姿勢を象徴している。
糸林先生のおもな著書の紹介
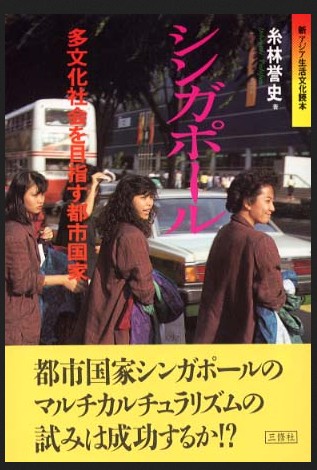
「多文化主義」は理想か、統治の装置か。CMIO(中国・マレー・インド他)モデルで管理されるシンガポール。本書は、ラッフルズの植民地都市建設から、HDB(公共団地)による国民統合、カンプン(村)への郷愁までを読み解きます。国家が設計する「住まい」や「言語」が、いかに人々のアイデンティティを書き換えていくか。都市国家の実験から、21世紀の「共生」と「国家」のあり方を鋭く問う一冊です。
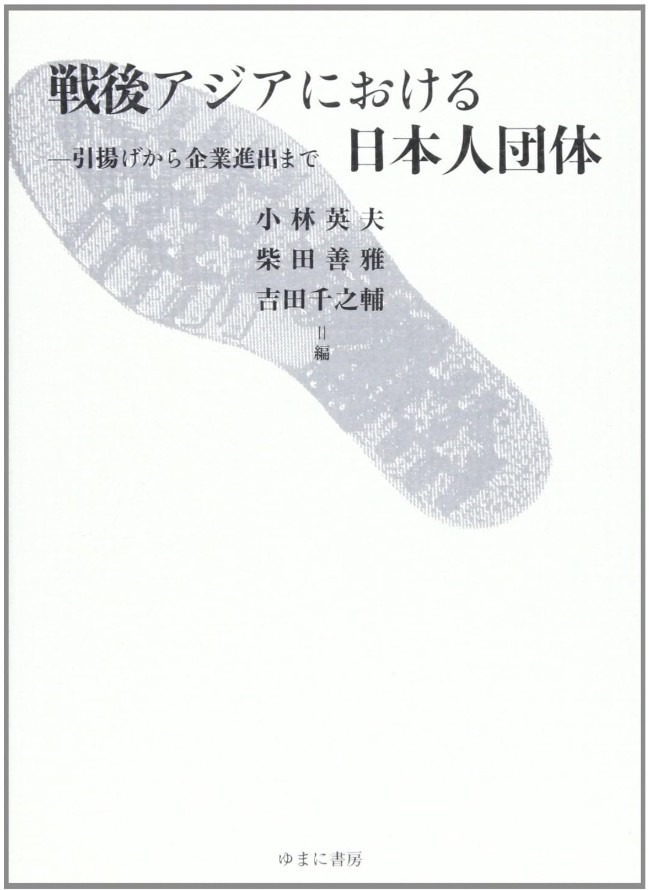
戦後アジアと日本の関係を、政府でも企業でもない「日本人団体」から捉え直す画期的論集。先生が担当したシンガポールの章では、日本人墓地の管理という「死者への責務」を起点に、戦後の日本人会や日本人学校がいかに再編されたかを歴史的に位置づけます。経済成長のインフラとしての側面だけでなく、断絶を超えてコミュニティが再生するプロセスとして組織を読み解く。歴史の縦軸で現在を視る、リベラーツならではの視座です。

第56回毎日出版文化賞に輝く日本最大級の知の集積『岩波イスラーム辞典』。先生は「シンガポール」を担当し、近隣の大国とは異なる、都市国家の少数派としてのマレー系社会の独自性を第一人者の視座から描き出します。イスラーム世界を単一の色で見ず、地域ごとの微細な差異と多様性を深く理解する。広大な知の森へ分け入るための、イスラーム研究必携の基本図書です。

通常3,000円の講座「文化理論の道具箱」を、 今だけ無料でプレゼントします。
なぜ、あの会議はいつも同じ結論にしかならないのか? その答えを解き明かすための有料講座(60分)を、リベラーツプレオープン記念として期間限定で無料公開します。 クレジットカード登録は不要。1分で視聴を開始できます。

「人類学的思考を武器にする」
無料の体験講座(全20回)
「正しい判断」が現場に響かない理由 、知りたくありませんか? その答えは「人類学的思考」にあります。
組織の「暗黙のルール」を読み解き、 「現場を動かす判断力」を手に入れる 。
全20回の連続講座『人類学的思考を武器にする』まずは無料体験で、 思考のOSをアップデートする感覚を掴んでください。

自律したキャリアという「庭」の手入れを、ここから。
仕事とは、与えられるものではなく、自らの手で耕し、育てていくものです。 組織文化論とキャリア開発研究の知見を統合した、大人のための「意味の再構築」体験へようこそ。講師は、国家資格キャリアコンサルタントのいとばや先生。
リベラーツの講座サイト(liberarts.org)へ移動します。
クレジットカード登録不要。Googleアカウント等で30秒で開始できます。
