学習ガイド|リベラルアーツへの招待
序論:2010年、フランスの「記憶」の転回点
歴史とは、過去に起きた事実の羅列ではありません。それは現在という視点から再構成され続ける「語り」の総体です。フランス現代史において、第二次世界大戦中のヴィシー政権による対独協力(コラボラシオン)の記憶は、長らく国民的なアイデンティティを揺るがす「ヴィシー症候群(Le Syndrome de Vichy)」として、社会の深層に沈殿してきました。
その沈黙と葛藤の歴史において、2010年は極めて重要な分水嶺となる年でした。この年、フランス映画界は、1942年7月16日から17日にかけてパリで行われたユダヤ人一斉検挙「ヴェル・ディヴ事件(Rafle du Vel’ d’Hiv)」を主題とした二つの主要作品を世に送り出したからです。一つはローズ・ボッシュ監督の『黄色い星の子供たち(La Rafle)』、そしてもう一つが本稿で取り上げるジル・パケ=ブランネール監督の『サラの鍵(Elle s’appelait Sarah)』です。
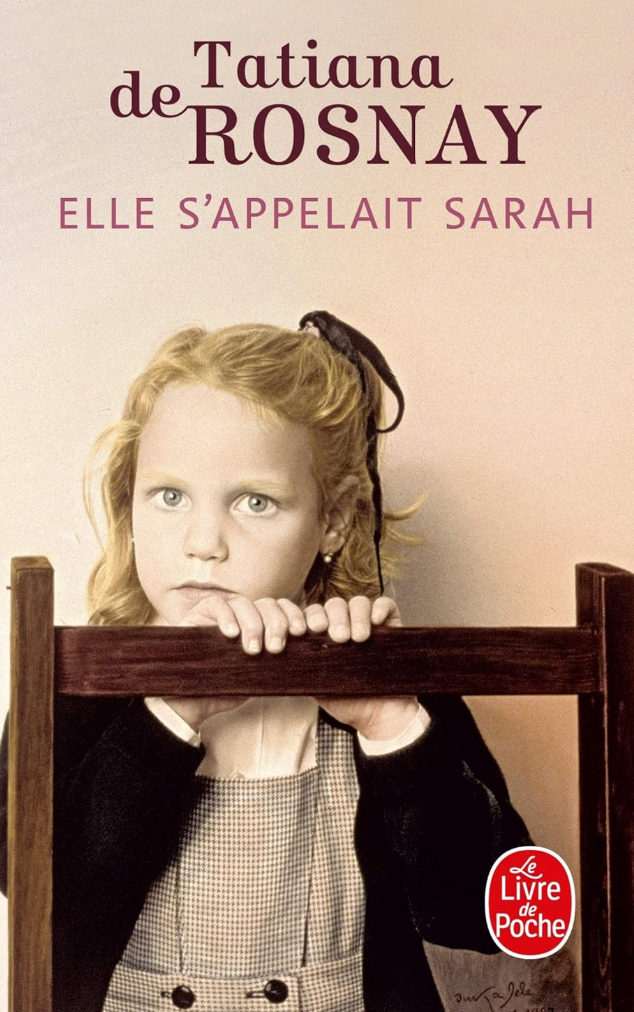
Elle s’appelait Sarah 2010
1995年、ジャック・シラク大統領がこの事件における「フランス国家の責任」を公式に認めてから15年。『サラの鍵』の公開は、フランス社会が自国の負の歴史といかに向き合い、それをいかに次世代へ継承しようとしているかを示す、一つのメルクマールとなりました。
本稿では、タチアナ・ド・ロネのベストセラー小説を原作とするこの映画を、単なる感動的なヒューマンドラマとしてではなく、「メモリアル・スタディーズ(記憶研究)」のテキストとして解読を試みます。マイケル・ロスバーグの「多方向的記憶」やアリソン・ランズバーグの「補綴的記憶」といった理論的枠組みを補助線とすることで、この映画が現代の私たちに提供する「記憶へのアクセス権」の本質が浮かび上がってくるはずです。
1. 歴史修正主義を超えて:ローラン・ジョリーの研究と映画のリアリズム
映画の中核をなすのは、ナチス占領下のパリで13,000人以上のユダヤ人がフランス警察によって検挙され、冬季競輪場(ヴェル・ディヴ)に監禁された史実です。映画はこの地獄絵図を、生存者の証言に基づき、圧倒的な「騒音」と「劣悪な衛生状態」によって再現しました。しかし、歴史学の視点から見ると、そこには映画的な選択と排除が存在します。
歴史家ローラン・ジョリー(Laurent Joly)の2022年の研究『La Rafle du Vel d’Hiv』は、この事件に関する従来の理解に重要な修正を迫っています。ジョリーによれば、この作戦はナチスの要求に基づくものであったものの、その実行プロセスにおいてはヴィシー政権下のフランス警察が高度な「自律性」を維持しようと画策していました。特筆すべきは、当初ドイツ側が要求していなかった「子供の移送」を、ピエール・ラヴァル首相らが「家族を引き離さない」という人道的(に見せかけた)配慮と、収容人数の帳尻合わせのために自ら提案したという行政的な冷徹さです。

La rafle du Vel d’Hiv: Paris, juillet 1942 2023
映画はこの政治的決定のプロセスを背景に退かせ、あくまで被害者である少女サラの視点に徹します。ここで興味深いのは、ジョリーが指摘する「相対的失敗」の側面です。計画では約27,400人の検挙が見込まれていましたが、実際には12,884人(約47%)にとどまりました。これは、事前に情報を漏らした警察官や、ユダヤ人を匿った近隣住民の「微細な抵抗(micro-decisions)」が存在したことを示唆しています。
映画『サラの鍵』は、この複雑な歴史のレイヤーを、アパートの鍵をめぐる「個人の罪悪感」へと収斂させています。これは歴史の矮小化でしょうか? 否、むしろ巨大すぎる構造的暴力を、個人の身体的感覚として理解可能なサイズへと翻訳する試みと言えるでしょう。
2. 「補綴的記憶(Prosthetic Memory)」の装置としてのジュリア
本作の最大の特徴は、物語が1942年のサラと、2002年(映画設定では2009年)のパリに暮らすアメリカ人ジャーナリスト、ジュリア・ジャーモンド(クリスティン・スコット・トーマス)の視点を交互に描く「通時的」な構成にあります。
なぜ、フランスの悲劇を描く物語の主役が、アメリカ人女性でなければならなかったのでしょうか。ここで有効なのが、アリソン・ランズバーグが提唱した「補綴的記憶(Prosthetic Memory)」という概念です。
補綴的記憶とは、マスカルチャー(映画、博物館、小説など)との接触を通じて、個人が直接体験していない過去の出来事の記憶を、あたかも自分の体験(義肢=Prosthesis)のように身体に接ぎ木する現象を指します。ジュリアは、ユダヤ人でもフランス人でもなく、事件の当事者性を持たない「部外者」です。これはまさに、スクリーンを見つめる私たち観客の立ち位置と重なります。
ジュリアは取材を通じて、そして夫の家族が隠蔽してきた過去(サラのアパートを接収して暮らしていた事実)を暴く過程で、サラのトラウマを深く内面化していきます。彼女の身体(妊娠中の胎児)は、過去の死(サラの弟ミシェル)と未来の生を接続する「記憶の有機的な媒介」として機能します。映画はジュリアというフィルターを通すことで、文化的・民族的背景の異なる観客に対して、ホロコーストの記憶への情動的なアクセス権を付与しているのです。
これは「記憶の私有化」や「当事者性の簒奪」という批判を招くリスクを孕んでいますが、ランズバーグによれば、血縁や民族を超えた「連帯(Solidarity)」の可能性を開く重要なプロセスでもあります。私たちはジュリアを通じて、他者の痛みを「我がこと」として想像する訓練を受けていると言えるでしょう。
3. 「ポスト記憶」の沈黙と、鍵が開くもの
映画のもう一つの重要な軸は、マリアンヌ・ハーシュが提唱する「ポスト記憶(Postmemory)」の問題系です。ポスト記憶とは、トラウマ的な出来事を直接体験した世代(第一世代)の沈黙や断片的な語りを通じて、その圧倒的な影響下で育つ第二世代以降の記憶構造を指します。
本作においてポスト記憶を体現するのは、サラの息子であるウィリアム・レインズフェルド(エイダン・クイン)です。彼は母がユダヤ人であったことや、彼女が抱えていた凄惨な過去(弟を納戸に閉じ込め、死なせてしまったという原罪意識)を全く知らされずに育ちました。
ジュリアによってもたらされる真実は、ウィリアムにとって自己のアイデンティティを根底から覆す暴力的な啓示となります。「知らないままでいたかった」という彼の拒絶は、多くのサバイバーの子供たちが直面する「沈黙によって守られてきた平穏」と「知ることの痛み」の相克をリアルに映し出しています。
映画のタイトルにある「鍵」は、弟ミシェルを閉じ込めた物理的な鍵であると同時に、サラの心の中に封印されたトラウマへのアクセスキーでもあります。ジュリアがその鍵を(比喩的に)回したとき、そこから溢れ出したのは、単なる悲劇の事実だけではありませんでした。それは、親世代が子供を守るためにあえて選んだ「忘却」という名の愛と、それでもなお滲み出てしまう苦痛の連鎖でした。
ウィリアムが最終的に母の過去を受け入れ、ジュリアと精神的な和解を果たす結末は、フィクションならではの救済(カタルシス)かもしれません。しかし、それは「記憶の継承」こそが、世代を超えたトラウマを治癒する唯一の可能性であることを示唆しています。
4. 映像の倫理学:「見せない」ことの雄弁さ
映画的な表象において、ホロコーストをどう描くかという問題は、常に「表象不可能性」の議論と隣り合わせです。アウシュヴィッツのガス室や死体の山を直接的に再現することは、倫理的に許されるのか?
パケ=ブランネール監督は、この難題に対して一つの回答を提示しています。それは、サラが納戸を開け、弟の遺体を発見するクライマックスシーンにおける「慎み(pudeur)」の演出です。カメラは納戸の中にあるはずの腐敗した遺体を直接映しません。映し出されるのは、それを見たサラの凍りついた表情と、絶叫だけです。
ラカン精神分析の用語を借りれば、ここには「現実界(The Real)」――象徴化もイメージ化もできないトラウマの核――が出現しています。観客は何も見せられないからこそ、サラの表情を通じて、そこにある「見えない恐怖」を最大限に想像させられます。これは、スティーヴン・スピルバーグが『シンドラーのリスト』で試みたような直接的なリアリズムとは対極にある、示唆と欠如による表象の倫理と言えるでしょう。
5. 多方向的記憶の地平へ:なぜ今、この映画なのか
最後に、マイケル・ロスバーグの「多方向的記憶(Multidirectional Memory)」の視点から本作を位置づけ直してみましょう。ロスバーグは、ホロコーストの記憶を特権化し、他の歴史的トラウマと競合させるのではなく、それらを相互に参照し合わせることで、新たな連帯が生まれると説きます。
『サラの鍵』は、一見するとホロコースト特有の物語です。しかし、2010年のフランスという文脈において、この映画はアルジェリア戦争や植民地支配といった、フランスが抱える他の「抑圧された記憶」とも共鳴する空間を作り出しました。パリのど真ん中で警察が市民を検挙し、収容所へ送ったという事実は、1961年のパリ虐殺(アルジェリア系住民への弾圧)の記憶をも呼び覚ますからです。
また、本作が「シネマ・モンド(Cinéma-monde)」――国境を越えたハイブリッドな映画制作――の一例として、英米圏を中心に世界的なヒットを記録したことも重要です。これは、特定の国民国家の歴史(ナショナル・ヒストリー)であったヴェル・ディヴ事件が、普遍的な人権や家族の物語としてグローバルに共有され始めたことを意味します。
結論:記憶の扉を開け続けるために
映画『サラの鍵』は、歴史の教科書に記述された「13,000人」という統計的な数字に対し、物語の力を使って「顔と名前」を取り戻す試みでした。
そこには、「ホロコーストのアメリカ化(エンターテインメント化)」という批判も確かに存在します。ジュリアの現代的な悩みが歴史の重みを希釈しているという指摘も妥当でしょう。しかし、歴史の証言者が次々と世を去り、「証言の時代」が終わりを告げようとしている今、私たちに必要なのは、完全無欠な史実の再現だけではありません。
必要なのは、私たちのような「部外者」が、過去の痛みに触れ、それを自らの問題として思考するための「回路」です。ジュリア・ジャーモンドは、まさにその回路そのものです。彼女が手にした鍵は、サラの物語の扉を開けただけでなく、現代を生きる私たちが歴史に対して負っている倫理的責任への扉をも開いているのです。
私たちがこの映画から受け取るべきは、過去を「知った」という満足感ではなく、知ってしまったからにはもはや無関係ではいられないという、静かな、しかし重たい「記憶の義務」のバトンなのかもしれません。
Reference:
- Laurent Joly, “La Rafle du Vel d’Hiv: Paris, juillet 1942” (2022)
- Alison Landsberg, “Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture” (2004)
- Marianne Hirsch, “The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust” (2012)
- Michael Rothberg, “Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization” (2009)



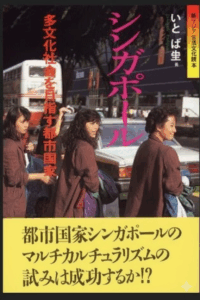
コメント