日本の教養教育とリベラーツの挑戦
「パンの耳」の呪縛と解放 ――日本における教養教育の未完のプロジェクト
日本の大学教育において、「教養(一般教育)」は長らく不遇な扱いを受けてきました。 かつて多くの学生にとって、教養科目とは「専門課程に進むための通過儀礼」であり、講義内容は退屈で、単位さえ取れればよい「パンの耳」のような存在だと揶揄されてきました。
なぜ、欧米では「自由市民の必須スキル(リベラルアーツ)」として尊重される知が、日本では「おまけ」のように扱われてしまったのでしょうか? 第2回となる本稿では、戦後日本の教育史を紐解きながら、AI時代における教養の「解放」について論じます。
1. 戦後改革の理想と、「専門」偏重の壁
時計の針を1949年の新制大学発足時に戻しましょう。 戦後の学制改革において、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)のCIE(民間情報教育局)は、米国のリベラルアーツ・カレッジをモデルとした「一般教育(General Education)」の導入を強く推進しました。これには、戦前の専門偏重教育が視野の狭い専門家を生み出したことへの反省と、民主主義社会の担い手を育成するという崇高な理想がありました。
しかし、現実は理想通りには進みませんでした。 旧制高校の伝統を継承した教養部と、実学志向の強い専門学部との間で、深刻な対立構造が生まれたのです。多くの大学において、教養課程は「専門教育に入る前の準備段階」として低く位置づけられました。美味しいサンドイッチ(専門教育)を食べるために我慢して食べる「パンの耳」。この不幸なメタファーは、日本の教養教育が抱える構造的な欠陥を象徴しています。
2. 1991年の衝撃:大綱化と「教養の空洞化」
この歪みが決定的になったのが、1991年の大学設置基準の「大綱化」です。 文部省(当時)は規制緩和の一環として、一般教育と専門教育の区分を廃止しました。本来の意図は、各大学が自由にカリキュラムを設計し、教養教育を活性化させることにありました。
しかし、多くの大学が選んだのは「教養部の解体」でした。 「教養部」という組織が廃止され、教員は各専門学部へ所属変更となりました。その結果、体系的な教養教育を行う主体が消失し、専門科目の早期履修が進む一方で、教養科目は縮小・形骸化しました。これを教育社会学者の吉田文氏らは「教養教育の空洞化」と指摘しています。
3. 「くさび形」教育への転換と、新たな兆し
しかし、2000年代以降、振り子は再び戻り始めます。急速なグローバル化と社会課題の複雑化により、「専門知識だけでは解決できない問題」が顕在化したからです。
象徴的なのが、東京工業大学(現・東京科学大学)の取り組みです。同大学は2016年に「リベラルアーツ研究教育院」を設置し、学部から大学院まで教養教育と専門教育が並走する「くさび形教育」を導入しました。入学直後の「教養」で終わるのではなく、専門性が高まる博士課程の学生こそが、より高度な教養(リーダーシップや倫理)を学ぶという設計です。 また、東京大学においても伝統的な「遅い専門化(Late Specialization)」の理念が見直され、前期課程(教養学部)における学際的な学びの価値が再評価されています。
4. 未完のプロジェクトを継承する
戦後70年を経て、ようやく日本でも「パンの耳」は「主食」としての地位を取り戻しつつあります。 しかし、大人の学び(リカレント教育)の現場ではどうでしょうか? まだまだ「即効性のあるスキル(=具)」ばかりが求められ、それを支える「教養(=パン)」の価値は見過ごされがちです。
AI時代において、専門知識の賞味期限はますます短くなっています。だからこそ、時代に左右されない普遍的な知性――かつて「パンの耳」として捨てられていた部分――こそが、これからのキャリアを支える最強の栄養源となるのです。
次回は、視点を世界に移します。米国や欧州のトップエリートたちは、どのようにして最先端のテクノロジーと古典的なリベラルアーツを「統合」しているのか。その実態に迫ります。
(第3回へ続く)



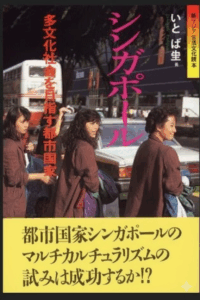
コメント