沖縄・琉球の知恵
第1回:なぜ今、個人の「語り」が重要なのか?
日本における「ライフヒストリー」と「生活史」の深層
はじめに:数字の彼方にある「リアリティ」へ
「データは嘘をつかない」 ビジネスの現場や政策決定の場において、この言葉はしばしば絶対的な真理として語られます。ビッグデータやAI解析が全盛の現代において、数値化されたエビデンスは最強の意思決定ツールです。しかし、私たちは同時に、数字だけでは決して捉えきれない「何か」があることも肌感覚として知っています。
アンケート調査で「満足度4.5」と答えた顧客が、実はそのサービスを利用するたびに深い孤独を感じていたとしたら? 統計上の「貧困率」に含まれる一人の人間が、その状況下で驚くほど豊かな人間関係と独自の生存戦略を築き上げていたとしたら?
私たちが本当に知りたいのは、表層的な数値の奥にある、生身の人間の「切実な理由(わけ)」ではないでしょうか。
今、社会学の領域で「生活史」や「ライフヒストリー(Life History)」と呼ばれる調査手法が、静かな、しかし確実な熱量を持って注目されています。これらは単なる「昔話の記録」や「個人の思い出語り」ではありません。「たった一人の語り(N=1)」を通じて、その背後にある巨大な社会構造や歴史のうねりを逆照射する、極めてスリリングな知的営みなのです。
本連載では、この「個人の語りを聞く技術」について、学術的な系譜と実践的な技法の両面から深く掘り下げていきます。第1回となる今回は、特に日本における独自の発展の歴史を紐解きながら、「ライフヒストリー」と「生活史」という似て非なる概念が、どのようにして現代の私たちの「聞く力」を形作ってきたのかを詳らかにします。
1. 「ライフヒストリー」の源流:シカゴ学派から日本へ
まず、世界標準の学術用語としての「ライフヒストリー(Life History)」の出自を確認しておきましょう。この概念が社会学の主要なメソッドとして確立されたのは、20世紀初頭のアメリカ、シカゴ大学(シカゴ学派)においてでした。
記念碑的研究とされるのが、W.I.トマスとF.ズナニエツキによる『欧米のポーランド農民』(1918-1920年)です。彼らは、ポーランドからアメリカへ渡った移民たちが直面した激しい社会変動や家族の解体・再組織化を分析するために、統計データではなく、移民たちが交わした膨大な手紙や自伝を主要なデータとして採用しました。彼らが目指したのは、個人の主観的な記録(Personal Documents)を通じて、社会全体の構造変動を読み解くことでした。
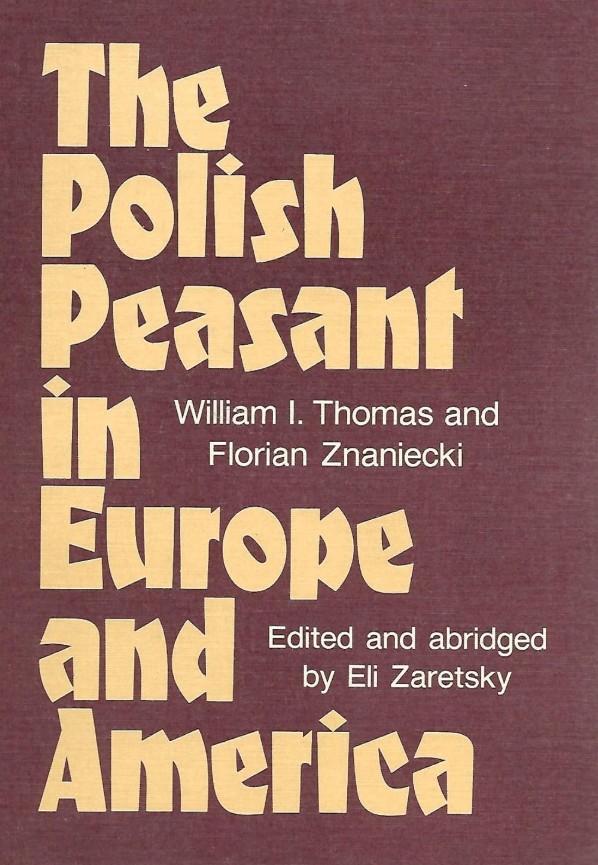
この「個人の記録から社会構造を見る」という視点は、戦後の日本社会学にも輸入されました。しかし、日本にはそれを受け入れるだけの、独自の豊饒な土壌がすでに存在していたのです。それが、民俗学と「生活記録運動」、そして戦後社会学の系譜です。
2. 日本独自の土壌:「民俗学」と「生活記録運動」
日本における「生活史」という言葉の響きには、欧米の「Life History」にはない独特の重みと湿り気があります。それは、この言葉がアカデミズムの輸入概念としてだけでなく、在野の実践の中から立ち上がってきたものだからです。
① 宮本常一と「生活誌」:無字社会の記録
日本の生活史研究を語る上で欠かせないのが、民俗学者・宮本常一(1907-1981)の存在です。 宮本は、師である柳田國男が「心(民間伝承や信仰)」の分析を通じて日本人のアイデンティティ(「私たちはなにものか」)を探求したのに対し、生産用具などの「もの(民具)」と、徹底して現地を歩く「足」を通じて、庶民の生活変遷を記録しようとしました。
柳田が「変わらない伝承」を記録しようとした(民俗誌)のに対し、宮本は「変化していく生活の実態」を動態的に捉える「生活誌(生活史)」を提唱しました。 宮本にとっての対象は、文字を持たない「無字社会」の庶民たちでした。権力者が書き残す「大きな歴史」に対し、伝承や記憶によってのみ保持されてきた庶民の「小さな歴史」を文字化すること。特に、定住農民だけでなく、漁民や「世間師(せけんし)」と呼ばれる移動者たちのダイナミズムを記録することを目指しました。

宮本の代表作『忘れられた日本人』に見られるように、彼の「聞き書き」は、対象者の語りをそのまま記述する文学的なスタイルをとっています。これは、客観的な事実の記録であると同時に、語り手と聞き手(宮本)との人間的な交流の中で立ち上がる「物語」としての側面を強く持っていました。
② 戦後の「生活記録運動」:書くことによるエンパワーメント
もう一つ、日本の生活史研究の土壌となったのが、1950年代を中心に全国で展開された「生活記録運動」です。 これは、炭鉱労働者、工場の労働者、農村の主婦、被差別部落の人々などが、自らの貧困や苦難、生活実態をありのままに「綴る(書く)」ことで問題を共有し、解決へ向かおうとした実践的な運動でした。
ここでは、「書く」ことは単なるデータ提供ではありませんでした。生活者が自ら「書く主体」となり、自らの置かれた状況を客観視し、生きる力を獲得する(エンパワーメント)プロセスそのものだったのです。この「生活者の主観的真実」を重視する姿勢は、後の日本の生活史研究に決定的な倫理的基盤を与えました。
3. 戦後社会学の金字塔:中野卓による「生活史法」の確立
宮本常一らが民俗学のフィールドで「生活史」を掘り起こし、生活記録運動が労働者の主体形成を促していた頃、アカデミズムの社会学においても、個人の語りを社会科学の正統なデータとして位置づけるための格闘が始まっていました。その中心にいたのが中野卓(1920- )であり、それを理論的に体系化したのが有末賢(1953- )です。
① 中野卓と『口述の生活史』:問わず語りの技法
戦後日本の生活史研究における記念碑的作品とされるのが、中野卓による『口述の生活史 ある女の愛と呪いの日本近代』(1977年)です。中野はこの著作を通じて、シカゴ学派の影響を受けつつも、日本独自の文脈で「個人の語り」を社会学的な分析の遡上に載せる方法論を確立しました。

中野の方法論の最大の特徴は、「問わず語り」の重視です。『口述の生活史』において、中野は質問者としての自分を極限まで消し去り、語り手(内海松代)が自発的に語る言葉を全体の約6割も占める形で構成しました。 武笠俊一の研究によれば、これは単なる「放置」や「聞き手の不在」ではありません。中野は、語り手がすでに40年前に自伝的な手紙を書いていた事実を知りながら、あえてそれを参照せず、今の彼女がどう過去を「再構成」するかを注視しました。中野の「消極的な姿勢」は、語り手の内面にある「語るべき動機(思い)」を純粋な形で引き出すための、計算され尽くした「抑制的な技法」だったのです。
② 歴史的現実の再構成
現代の構築主義的なアプローチ(事実かどうかよりも、どう語ったかを重視する立場)とは異なり、中野はあくまで「歴史的現実(Historical Reality)」の記述を目指しました。 彼は、本人が語った「ライフストーリー(主観的真実)」をそのまま事実とは見なしませんでした。研究者が客観的な社会史資料や文献と照合し、緻密な注釈を加えることで、初めて客観性を帯びた「ライフヒストリー(生活史)」という作品に昇華できると考えました。つまり中野にとって生活史とは、個人の主観と歴史的客観を、研究者が媒介となって縫合する、厳密な実証科学の営みだったのです。
③ 有末賢と「意味の社会学」
中野卓の薫陶を受けた有末賢(慶応義塾大学)は、2012年の『生活史宣言』において、生活史研究を単なる調査技法から、社会学的な理論構築の場へと高めました。 有末は、生活史研究の核心を「意味論(Semantics)」に置きました。彼は、個人の語りを単なる事実の羅列としてではなく、その人が生きた時間の中で出来事にどのような「意味」を与え、記憶を変容させてきたかを探求するプロセスとして定義しました。
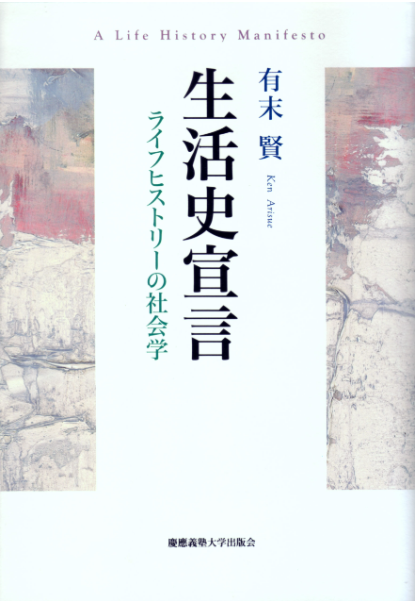
片桐雅隆が指摘するように、有末の議論の背景には、高度経済成長が終わり、「進歩」や「革命」といった社会全体の「大きな物語」が解体したという時代認識があります。社会全体の目標が見えにくくなったポストモダン状況において、個々人がバラバラに紡ぎ出す「小さな物語(生活史)」こそが、リアリティを捉える唯一の手がかりになるという認識です。 また有末は、過去を振り返って再構成された「生活史」と、日記や手紙のようにその瞬間につづられた「ライフ・ドキュメント(生の記録)」を対比させることで、人間の意識が時間とともにどう変容するかを立体的に捉える視座を提供しました。
4. 「方法論的転回」:桜井厚と「ライフストーリー」の誕生
1980年代以降、日本の生活史研究は新たなフェーズに入ります。それが桜井厚(中京大、千葉大)による「ライフヒストリー」から「ライフストーリー」への転換です。

中野卓が「事実の検証」を重視し、語られた内容を歴史的事実と照らし合わせて「再構成」することを目指したのに対し、桜井は「語られたこと(Narrative)」そのものの自律性に注目しました。
対話的構築主義(Dialogical Constructionism)
桜井が提唱した「対話的構築主義」は、インタビューを単なる「情報の採集」とは見なしません。インタビューとは、聞き手と語り手の相互行為(コミュニケーション)によって、その場限りの「現実」が構築されるプロセスであると捉えます。
- 事実か虚構かは問題ではない: 桜井の立場では、語られた内容が客観的な歴史的事実と合致しているかどうか(Fact)よりも、語り手がその出来事をどう意味づけ、どう語ったかという「主観的なリアリティ(Reality)」が重要視されます。たとえ記憶違いや誇張があったとしても、その人が「そう語った」という事実の中にこそ、その人のアイデンティティや価値観が現れるからです。
- 聞き手の存在: 従来の調査では、聞き手は透明な存在(黒子)であることが望ましいとされてきました。しかし桜井は、聞き手もまた語りの構築に関与する「共犯者」であり、調査の重要な構成要素であると位置づけました。
この転換により、日本の生活史研究は「歴史的事実の空白を埋める(オーラルヒストリー的側面)」だけでなく、「個人が社会をどう意味づけて生きているか(現象学的側面)」を解明する高度な質的調査へと進化しました。
5. 現代の到達点:岸政彦と「他者の合理性」
そして現代。岸政彦は、これら先人たちの議論を受け継ぎつつ、生活史研究をよりラディカルな(根源的な)方向へと推し進めています。
岸氏は生活史をシンプルに「ひとりの人間の、人生の語り」と定義します。 岸氏のアプローチの最大の特徴は、「分析」や「要約」への慎重な姿勢と、「他者の合理性」への着目です。
① 「ウラ」を取らない:根本的経験論
岸は、生活史調査において「ウラを取る(事実確認をする)」必要はないと断言します。 これは中野卓の実証主義的な時代とは対照的です。なぜなら、生活史の目的は歴史の教科書を作ることではなく、その人がその出来事をどう経験し、どう感じて泣いたり笑ったりしたかという「生きられた経験(Lived Experience)」のディテールに触れることだからです。 「映画のタイトルが間違っている」といった些細な事実の誤りよりも、「その映画を見て泣いた」という経験の切実さこそが重要なのです。これはウィリアム・ジェームズの「根本的経験論(Radical Empiricism)」——主観と客観を分ける前の「経験そのもの」をリアリティとする考え方——とも共鳴します。
② 「他者の合理性」の理解
私たちはしばしば、自分と異なる背景を持つ人(貧困、差別、あるいは異なる文化圏の人々)の行動を見て、「非合理的だ」「理解できない」と切り捨ててしまいます。 しかし、生活史の聞き取りを通じて、その人が置かれた状況、生きてきた文脈を深く知れば、一見不可解な行動にも、その人なりの切実な理由——「他者の合理性」——があることが見えてきます。 人は誰しも、与えられた状況の中で、少しでも「よりマシなもの」を選んで懸命に生きています。生活史調査とは、この「他者の合理性」に触れ、分断された他者への想像力を取り戻す実践なのです。
③ 市民による記録:『東京の生活史』
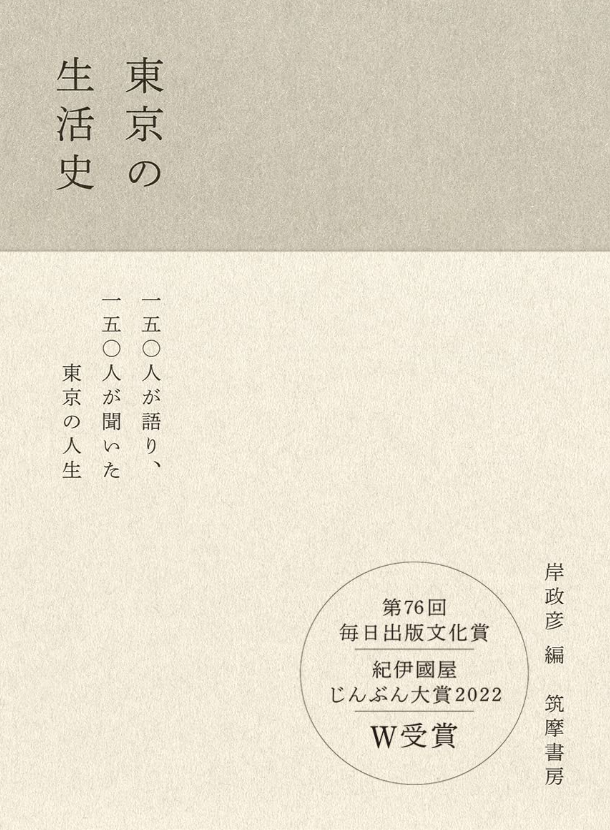
岸が監修した『東京の生活史』(2021年)は、専門家ではない150人の一般市民が聞き手となり、150人の語り手の人生を記録した1200ページを超える大著です。 これは、かつて宮本常一が目指した「庶民が歴史を作る」という思想と、生活記録運動が目指した「書くことによるエンパワーメント」、そして桜井厚が拓いた「対話による構築」という日本の生活史研究の系譜が、現代的な形で結実したプロジェクトと言えるでしょう。
まとめ:日本における「生活史」の独自性
欧米の「ライフヒストリー」が、都市問題や移民研究という社会学的課題解決のツールとして発展したのに対し、日本の「生活史」は以下のような独自の系譜を辿ってきました。
- 民俗学的基盤(宮本常一): 消えゆく「無字社会」の記録と、漂泊する人々への温かなまなざし。「足」で稼ぐフィールドワークの確立。
- 実証と理論の統合(中野卓・有末賢): 生活記録運動の影響を受けつつ、個人の語りを「歴史的現実」として再構成する厳密さと、意味論的な深みへの昇華。
- 現象学的深化(桜井厚・岸政彦): 客観的事実よりも「語り口」や「主観的リアリティ」を尊重し、社会の分断を越境しようとする思想的な営み。
日本の生活史研究は、単なるデータ収集法ではありません。それは、数値化できない人間の尊厳と、割り切れない人生の複雑さを、そのままの形で社会の中に位置づけようとする、「知的な対話の運動」なのです。
【参考文献】
- 中野卓『口述の生活史』(御茶の水書房, 1977)
- 宮本常一『忘れられた日本人』(岩波文庫, 1984)
- 桜井厚『インタビューの社会学 ライフストーリーの聞き方』(せりか書房, 2002)
- 岸政彦『生活史の方法』(ちくま新書, 2025)
- 有末賢『生活史宣言』(慶應義塾大学出版会, 2012)
- 武笠俊一「『問わず語り』の背後に潜むもの—『口述の生活史』成立の謎に迫る」(『人文論叢』26, 2009)
- 片桐雅隆「書評『生活史宣言』 生活史研究を社会学史のなかに位置づける」(『現代社会学理論研究』, 2013)
- 蘭信三「日本におけるオーラルヒストリーの展開と課題」(『日本オーラル・ヒストリー研究』11, 2015)
- 江頭説子「社会学とオーラル・ヒストリー」(『大原社会問題研究所雑誌』585, 2007)



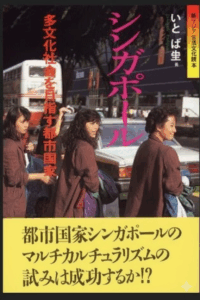
コメント